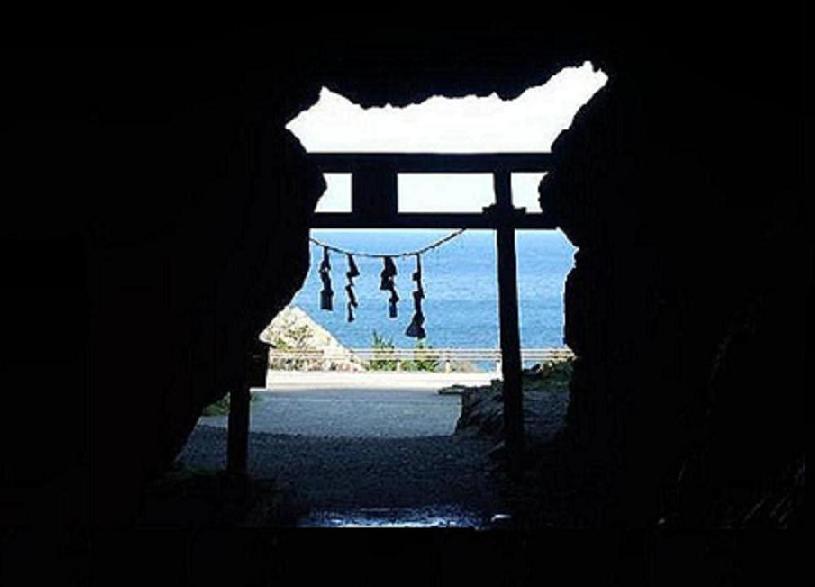
『空海マオの青春』論文編
後半第 10
プレ「後半」その4(二)の2
本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。
『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第280 ―論文編 後半10号
(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)
原則月1回 配信 2024年12月04日(水)
『空海マオの青春』論文編 後半 第10号 その4「『空海論』前半のまとめ(二)-2」
前半のまとめ二回目。これからどうやって謎を解いたか、具体的に語っていきます。
まずは『聾瞽指帰』の蛭牙公子と登場人物に施された戯画化について。
余談ながら謎解きと言えば、探偵や刑事の推理小説・ドラマが一般的です。
謎解きはだいたいラストに明かされる。その説明を聞くと、ときに「なーんだ」と思うことがあります。
今回空海に対する私の謎解きに関しても読者はそうつぶやくのではないか。
しかし、その前にいかに論理的に、段取りをもって推理するか。それが難しいし、大切なことと(私は)思います。
たとえば、最近視聴している中国ドラマ『成化十四年〜都に咲く秘密』は中国明朝を舞台とする時代劇なのに推理ドラマです。シャーロックホームズのような名探偵コンビが登場して様々な事件を解決します。
その中に国境近くで起こった馬どろぼうの話がありました。
北方から数百頭の馬を仕入れて運んできた7、8人の運搬人が宵闇の中、指定された牧場に到着。牧柵の中に馬を入れ、やっと仕事が終わったと、その夜は酒盛りをしてテントで寝た。すると、翌朝馬が1頭残らず消えていた。しかも、地面には馬糞一つ落ちていない。どろぼうは一体どうやって盗んだのか――未視聴の方はちょっと推理してみてください(^_^)。
なお、いつもの「ぼくの悪い癖」(杉下右京)で短くまとめようと思ったのに、書き始めたらどんどん長くなっています。(二)前期4つの謎の謎解きが最終的にいくつになるか見当がつかない(今のところは5節として年末には終えたい)ので、当初の公開日程を白紙に戻します。
「おいおい」とあきれることなく、お付き合いくだされば幸いです(^_^;)。
プレ「後半」その4 空海論 前半のまとめ
(一) 空海の前半生、前期(生誕〜23歳) 11月20日
(二) 前期4つの謎について(その1) 11月27日
前期4つの謎について(その2) 12月04日
前期4つの謎について(その3) 12月11日
前期4つの謎について(その4) 12月18日
前期4つの謎について(その5) 12月25日
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
本号の難読漢字
・唐泛(とうはん)・隋州(ずいしゅう)・『聾瞽指帰』(ろうこしいき)・『三教指帰』(さんごうしいき)・三教(単独のときは「さんきょう」、儒教・道教・仏教)
以下1〜5は『三教指帰』の登場人物
1 兎角(とかく)公 2 蛭牙公子(しつがこうし) 3 亀毛(きもう)先生 4 虚亡隠士(きょむいんし・亀毛先生と韻を踏めば「きょもういんじ」) 5 仮名乞児(かめいこつじ) 3は儒教、4は道教、5は仏教を語る。
・阿刀(あと)の大足(おおたり、空海の母方の叔父)・狭間(検索を)・筐底(きょうてい、箱の底)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************
後半第9号 プレ「後半」その4(二)「前期4つの謎について その2」
前置きの「馬どろぼう」の話、推理して見ましたか。
主人公の名探偵コンビとは(探偵に当たる)官吏3年目の若者「唐泛(とうはん)」と、秘密警察の武闘派「隋州(ずいしゅう)」。唐泛は次のように推理します。
まず数百頭の馬を入れた牧柵の中に、一晩とは言え馬糞が一つも落ちていないのはおかしい。よって、そこから馬を移動させたのではなく、最初から入れられなかったのではないか。運搬人は酒盛りをしてべろんべろんに酔っぱらったと言う。酒の中に眠り薬が入っていた可能性がある。ならば、誰か一人はどろぼうの配下だ。
草原の別のところに全く同じ牧柵とテントを設営する。そこに馬を持ち込ませ、深夜眠り込んだ運搬人を(本来の)牧場のテントに運んだ――と推理しました。翌朝目覚めれば当然馬はいない。
なるほどと思わせる名推理であり、その後巧みな方法で広大な草原から馬が保管されたところを見つけ出し、見事に事件を解決します。
この謎解きを聞いて私は正直「なーんだ」と感じました。しかし、推理はできなかった。
理由はどろぼうが「その牧場から盗んだに違いない」と思ったこと。そして「なぜ馬糞が一つも落ちていないのか」その理由を想像できなかったからです。
が、馬糞が一つも残っていない→そこに馬は連れて来られなかった――と現実を冷静に把握して推理すれば、この謎解きはさほど難しくなかったと言えます。
いわば、先入観をもって決めつけないこと、事実をしっかり見つめて論理的な疑問を提示し、妥当な説明(答え)を考える。そうすれば、不可解な謎と思われることも存外簡単に解けるようです。
そこで前節で取り上げた『聾瞽指帰』(改題『三教指帰』)における以下二つの謎。
A 兎角公が矯正しようとする自堕落にして放蕩者の甥「蛭牙公子」のモデルは?
B 三教を解説する登場人物の戯画化はなぜなされたのか。
既研究の答えはAに関して「モデルなし」であり、Bの方は(司馬遼太郎も含めて)言及がありません。三教論説者が語る言葉に目が向いて人物の外見、様子は「別に大したことではない」と考えたからでしょう。
そこで私が考えた謎解きは以下の通りです。
A 蛭牙公子とは儒教、道教、仏教を遍歴した若き空海マオである。
B 戯画化が施されたわけは作品が私小説として――作者周辺の事実として読まれることを恐れたから。
この証明は論文編前半「蛭牙公子=空海マオ」論〈その1〜その6〉(第8〜13節)をご覧ください。
特に『聾瞽指帰』原典には「蛭牙公子」を「甥」ではなく「姪」とした箇所があって「弘法も筆の誤り(^.^)」かと思わせるなど、論文最大のヤマです(^.^)。
それぞれ解説しておくと、1と2は重なっています。登場人物の戯画化を読み取ったからこそ、「モデル不明の蛭牙公子にも戯画化が施されているのではないか」と推理したのです。
『聾瞽指帰』の登場人物は以下の通り。
1.蛭牙公子[若者]……ギャンブル凶で自己チュー、女狂いの自堕落な若者。兎角公は母方のおじ。
2.兎 角 公[おじ]……甥の蛭牙公子をまっとうな人間にしようと教えを求める人。
3.亀毛先生[儒教]……兎角公と蛭牙公子に、忠孝と学問に励めば立身出世ができると儒教を説く。
4.虚亡隠士[道教]……儒教の問題点を指摘して無為自然、仙人を目指す道教こそ優れた教えと説く。
5.仮名乞児[仏教]……儒教も道教も浅薄な教えであり、無常観・八正道の仏教こそ苦しむ人を救う最高最上の教えであると説く。
これら人物のモデルとして「亀毛先生」は空海マオの叔父阿刀の大足、「仮名乞児」は空海自身と誰でもすぐにわかる(おそらく当時も)。
が、蛭牙公子、兎角公、虚亡隠士のモデルは不明。それが既研究の結論でした。
作品を丁寧に読めば、三教を語る人物に戯画化が施されていることに気がつく。
ならば、蛭牙公子にも戯画化があるのではないか――私はそう推理して蛭牙公子について書かれた次の説明から戯画化を除いてみました。極端なところを除けば、まーごく普通の若者となります。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ここに一人の若者がいる。「その心は狼のようにねじけ、人から教えられても従わない。心が凶暴で、礼儀など何とも思わない。賭博を仕事にし、狩猟に熱中し、やくざでごろつきのならずもので、思いあがっている。仏教でいう因果の道理を信ぜず、業の報いを認めない。深酒を飲み、たらふく食べ、女色に耽り、いつまでも寝室にこもっている。親戚に病人があっても、心配などしないし、よその人に対応して敬う気持ちもない。父兄に狎れて侮り、徳のある老人を小馬鹿にする」ような人間である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
現代ならこのような鼻つまみ者が親戚、知人の大人から説教されてすぐに改心するなんてめったにないでしょう。
しかし、意外にも蛭牙公子は儒教・亀毛先生の言葉を聞くと、「素晴らしい論説です。これからは心を入れかえ、一心に勉強したいと思います」と言い、兎角公も賛辞を惜しまず「私も生涯の糧として励みたいと思います」と決意を述べます。
二人は儒教以下三教の教えを聞くのは初めてと構想されています。
次に道教・虚亡隠士の言葉を聞くと「以後は道教を信奉して」、最後に仏教・仮名乞児の解説によって「仏教は最高の教えです。今後は仏教に衣替えしたい」と賛嘆平伏します。蛭牙公子は儒道仏三段階の教えに対して改心と決意を語るのです。
では空海マオはどうか。
彼は幼いころから儒教を学び、官僚を目指して大学寮に入学する。しかし、挫折して仏教に転進。ところが、座学とも言える南都仏教・仏教界に失望して山岳修験道修行に走る。その世界には仙人になることを夢見て神仙思想を語る道教信者がいる。空海マオも一度は道教に惹かれた。が、道教にも失望して仏教に回帰する。
つまり、空海マオは[儒教→道教→仏教]を揺れ動き、最終的に仏教を選びます。
一方、『聾瞽指帰』蛭牙公子の戯画化を取り払えば……、
彼は儒教に傾倒し、道教も素晴らしいと思い、最後は仏教に感嘆して「以後は仏教を学び、心のよりどころにしたい」と決意を語る。
これをまとめると、
空海マオ……儒教・道教・仏教の遍歴を経て仏教に至る。
蛭牙公子……儒教・道教・仏教の各説に感嘆して最後は「仏教こそ」と思う。
両者を比較すれば「蛭牙公子って空海マオその人じゃないか」とわかります。
どうです?
聞けば馬どろぼうの推理のように「なーんだ」と思いませんか。
しかし、この単純明快な真実にたどり着く研究者はいなかったようです。かの司馬遼太郎でさえ。
邪魔をしたのは先入観でしょう。「名僧空海が蛭牙公子のような自堕落人間のはずがない」とか、「聾瞽指帰は真面目な思想書であり論文である」と評価した。ゆえに、登場人物の戯画化は無視されたわけです。
逆に言うと、三教を語る登場人物の戯画化に気づかなければ、「蛭牙公子にも戯画化があるのでは」と思わないでしょう。
要するに、作品を丁寧に読み、その都度感じた疑問の[?]を書き込む。一読法読書術だから、私は戯画化に気づきました。
では、なぜ戯画化が施されたのか。
B 戯画化が施されたわけは作品が私小説として――作者周辺の事実として読まれることを恐れたから。
この推理は私でなければ出てこなかったかもしれません。
私は志賀直哉の『暗夜行路』を大学の卒論として取り上げ、以後も研究を続けて三十代後半に『わが青春の暗夜行路』と題して小冊子にまとめました。
その経験があったから思いついた推理だと思います。これも詳細は第8から13に詳しいので、ここは結論だけ書きます。
志賀直哉は自身の体験、事実を書く私小説作家です。彼は三十代の頃「祖父の子」として生まれた主人公「時任健作」を書こうと思います。
それは直哉(志賀家)における事実ではない。が、どうしても書きたい。そのわけは父との対立(最後は絶縁までする)のあまり、「自分は父の子ではないかもしれない」と疑問を抱いたこと、一方、祖父への尊敬の念から「祖父の子であったら良かったのに」と思ったことが根底にあります。
言わば『暗夜行路』とは私小説作家が客観小説を書こうとした試みなのです。
この構想を作品化した場合、最大の問題は作品が私小説として読まれることです。「志賀家ではそんなことがあったんだ」と大スキャンダルになって志賀家に多大の迷惑がかかります。
架空の構想に基づく小説なんだから作品は当然客観小説として描かれるはず。
ところが、直哉は私小説作家である。彼は自分の体験を使わないと実感を込めて描くことができない。
そこで父との対立を描いた私小説を次から次に発表して「父子対立の原因に出生の秘密などない」ことを印象付ける。最後に涙また涙の和解がなったことを『和解』に書いて公開する。
これでようやく祖父の子謙作という客観小説を書くことができる。そして『暗夜行路』冒頭には芸者・女給遊びをして友人と気まずい関係になった過去の事実を使った。
その際主人公謙作を「初めて女遊びをする童貞」としたのも「私小説ではない、客観小説だぞ」との気持ちからでした。
ところが、連載が始まると、直哉の友人である「白樺派」の同人たちから「正直に書いていないぞ」と批評されます。彼らは『暗夜行路』を私小説と受け取ったのです。直哉は怒りの言葉を発しています。
『暗夜行路』前編は祖父の子に苦しめられ、後編は「妻の過失」に苦しむ。こちらも直哉夫妻の事実ではないけれど、書きづらかったことは間違いなく、何度も中断して完成まで26年かかっています。
これと同じことが『聾瞽指帰』公開によって起こります。
マオは儒教から道教、そして仏教と三教の狭間を揺れ動き、最終的に仏教に進んだ。それぞれの良い点を書き、物足りない点は批判する。
仮名乞児はマオ自身だからいいとして儒教を語る亀毛先生のモデルに関して身近の読者はすぐ「あの儒学者大足さんだな」と気づく。
マオは儒教、儒者を批判したい。が、それはお世話になった大足叔父さんへの悪口でしかない。幼いころから長幼の序を叩きこまれたマオにとってそれは耐えがたいことでしょう。
そこで、儒者亀毛先生に戯画化を施した。下の者には堂々と自信たっぷりに人生や生き方を語りながら、上の者が現れると平身低頭する。そのような俗物人間に造形すれば、大足を知る知人友人は「この儒者は大足さんではないな」と思ってもらえる。それを期待しての戯画化だったのです。
こうなると儒者だけでなく、道教虚亡隠士も仏教仮名乞児にも戯画化を施す。自身を仮託する蛭牙公子にも。「モデルはいない」との思いは人物の名にはっきり示されています。亀に毛はなく、虚亡とは幽霊のこと。乞児に名はなく(仮名)、ヒル[蛭]に牙はない。
かと言って蛭牙公子が空海マオであることは気づいてもらわねばならない。
そこで兎角公はおじ、蛭牙公子は甥とした。それによって母方の叔父阿刀の大足、甥の空海マオの関係とわかる。蛭牙公子が兎角公の息子でも知人でもなく、「母方の甥ですよ」と強調されたのはそのせいです。
すなわち、空海マオは阿刀の大足を兎角公と亀毛先生、自身を蛭牙公子と仮名乞児に投影したのです。
では、戯画化を施せば直ちに作品を公開できるか。
今度は新たな問題が発生する(とマオは考えたはず)。それは大足叔父から「このような儒学者はいない」とか「お前は私をこんな低俗人間と思っていたのか」と一喝されることです。さー困った(^.^)。
素直に書いても戯画化して描いても、モデルにされた人は気持ちのいいものではありません。
そこで『聾瞽指帰』(巻物三巻)は完成したけれど、公開されることなく筐底深く仕舞われました。
この問題が解決されるには大足叔父に作品を読んでもらうしかありません。 「なんだ、これは」とあきれつつ、「確かにこんな儒者はいるかもしれん」と笑って許してくれるか。大足の許可を得て作品はようやく公開できるのです。
ただ、大足叔父に読んでもらう前に、空海マオにはもっと大きな問題がありました。
それは「本当に仏教に進むのか」というテーマです。
理屈としては「仏教こそ最高最上の教えであり、自分は仏教に進むしかない」と思う。だが、感情としては「まだその気持ちになれない。自信をもって心からこの道に進むと断言できない」悩みを抱えていました。
これは司馬遼太郎が読み取った「強くて傲慢な天才空海」のイメージを突き崩す「三教の狭間を揺れ動く悩めるマオ」の姿です。
私はどこからこの結論を引き出したか。それが『聾瞽指帰』仏教編に紛れ込んだ「儒教再解説」の部分です。
===================================
最後まで読んでいただきありがとうございました。
後記:「健康保険証は12月2日をもって廃止される。早めにマイナンバーカードを取得して保険証とヒモづけを。ただし、保険証代わりの『資格確認書』が届くのでそれを使えます」と言われています。すると、マイナンバーカードを持たない人から「資格確認書が届かないぞ!」と怒りの問い合わせが関係機関に殺到しているそうです。
これ肝心なことを言っていない。「資格確認書」が届くのは現行の健康保険証の期限が切れる直前(ほとんど来年のはず)。それまでは病院で現行の保険証を提出すれば良いのです。
実は私も問い合わせようと思ったМカードを持たない当人(^_^;)。
最近やっとテレビで解説を聞きました。同様の方がいるかもと思ってお知らせします。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)
『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信
詳しくは → PDF版配信について
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
後半第 11 へ
→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録