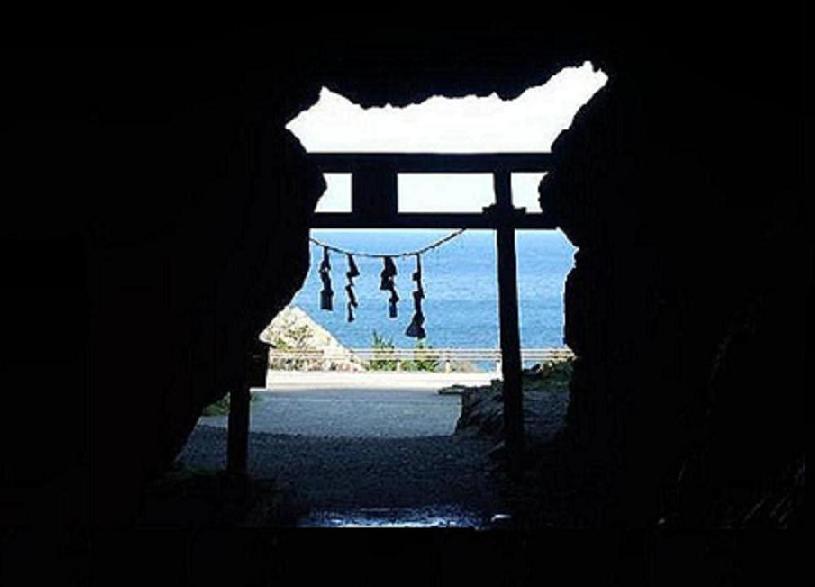
『空海マオの青春』論文編
後半第 11
プレ「後半」その4(二)の3
本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。
『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第280 ―論文編 後半11号
(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)
原則月1回 配信 2024年12月11日(水)
『空海マオの青春』論文編 後半 第11号 その4「『空海論』前半のまとめ(二)-3」
前半「4つの謎」について3回目。空海マオがめめしく悩む若者であったことを証明します。
空海23歳の著『三教指帰』は「儒道仏三教を比較した思想書」と言われます。
それに異論はないけれど、私は「戯画化が施された私小説」的要素を持っていると付け加えます。
私小説と理解すれば、司馬遼太郎が読み取った「強くて傲慢な天才空海」のイメージを覆す「三教の狭間を揺れ動く悩めるマオ」の姿が明らかになります。それが『聾瞽指帰』仏教編に紛れ込んだ「儒教再解説」の部分です。
儒教→道教→仏教と順を追って説明されながら、仏教編の中に再び儒教解説が繰り返される。論文としては下手くそな構成です。しかし、儒教と仏教の狭間で揺れ動いた心情を描こうとすれば仏教編にしか入らない。私小説と理解すれば何でもないエピソードなのです。
なお、本節は『空海マオの青春』論文編第13「蛭牙公子=空海マオ」論 その6の内容を若干修正したものです。
また、本節に引用した『三教指帰』文中の文言は福永光司『空海――三教指帰ほか』の口語訳を引用しましたが、若干変更があります。
プレ「後半」その4 空海論 前半のまとめ
(一) 空海の前半生、前期(生誕〜23歳) 11月20日
(二) 前期4つの謎について(その1) 11月27日
前期4つの謎について(その2) 12月04日
前期4つの謎について(その3) 12月11日
前期4つの謎について(その4) 12月18日
前期4つの謎について(その5) 12月25日
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
本号の難読漢字
・『聾瞽指帰』(ろうこしいき)・『三教指帰』(さんごうしいき)・三教(単独のときは「さんきょう」)・仮名乞児(かめいこつじ)・ 亀毛(きもう)先生・大足(おおたり)叔父・逼(せま)られる・退(しりぞ)く。夥(おびただ)しい・歎息(たんそく)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************
後半第9号 プレ「後半」その4(二)「前期4つの謎について その3」
『聾瞽指帰』仏教編の中で諸国放浪中の仮名乞児ことマオが長岡か平安京に戻った時でしょう、親戚の「或(あるひと)」に会います。
彼は仮名乞児――すなわちマオに対して次のように言って説教を始めます。
「主君への忠義、父母への孝行こそ人の生きる道であり、地位と財産を築き、妻子を持つことが一生の楽しみなのだ。ところが、君には親があり、主君もいるのに、孝養せず仕えようともしない。ただ浮浪者と乞食の群れの中に混じって祖先の名を汚し、後世に醜名を遺そうとしている。親戚一同はそなたに代わって穴にも入りたい思いだ。人は目をおおっているぞ。今からでも遅くない。すぐに忠孝の道に戻りなさい」と。
このリアルな言葉はどうでしょう。大学寮をやめ、仏門に入るところまでは良いとしても、乞食僧の格好でうろついているマオ。親戚(特に阿刀家の親戚)がたまたま彼と出会えば、一言説教せずにおれなかった――その様子が思い浮かびます。
今で言うなら、一人の若者がせっかく大学に入ったのに、勉強もせず、ぐだぐだ怠けて遊び暮らしてばかりいる(かに見える)。そのような学生に対して「しっかりせんかい」と叱咤する親とか(親に頼まれて説教する)親戚縁者の姿と重なります。
私にはマオと対面した人の言葉がそのまま記されているように思えます。正しく《私小説》ではありませんか。
〈或る人〉がマオに説いた言葉は確かに儒教の忠孝論ですが、亀毛先生が説いた忠孝と少々趣が違います。忠孝を勧めるのではなく、ドロップアウトした若者――マオに「忠孝に戻れ」と言っているのです。
ちなみに、この〈或る人〉ですが、「祖先の名を汚し」とか「親戚一同はそなたに代わって穴にも入りたい思い」とあるから、親戚の一人であることは間違いないでしょう。また、「浮浪者と乞食の群れの中に混じって」とあるから、マオが山岳修行中のときと思われます。
しかし、〈或る人〉とされた点だけでなく、私は別の理由で「亀毛先生=大足叔父」ではないと思います(この件についてはいずれ語ります)。
この説教に対して空海マオはなんと答えたか。
《仮名乞児》のマオは「憮然」として反問します。「ではお聞きしたい。忠孝とは一体なんですか」と。
〈或る人〉はひるむことなく答えます。「家庭にいるときはにこやかに親のご機嫌を伺い、外出や帰宅のたびに挨拶する。夏は涼しく冬は暖かいよう心を配り、全力を尽くして親に奉仕する。これが孝行であり、かつての主君もこの孝を実践して帝王となったのだ。
また、仕官する年になれば、孝を忠にかえ、主君のために命をささげる。もしも主君が過誤を犯せば、諫め論争する。このように主君を助けて出世を果たせば、栄誉は子孫に及び、名声は後世に伝わる。これこそ忠である」と。
これまた今の親御さんが不肖の息子や娘に聞かせたい説教ではないでしょうか(^_^)。「主君への忠」を「仕事」に置き換えれば、今でもそのまま使えます。
これが今から一千数百年前の奈良時代になされているのだから、ほんとに人の心は時代と関係ないことがよくわかります。
これに対して仮名乞児ことマオはどう反論したか。
「確かにそれが忠孝でしょう。私も人として父母の恩を片時も忘れたことがありません。親は年老い、家は傾き、親族も貧しい。私に託された期待を思うと胸が張り裂けんばかりです。
しかし、非力な私に肉体労働はできず、仕官しようにも才覚がありません。かつての君子ももはや存在しないではありませんか。大たわけの私はこれからどのように生きたらよいのか。ただ途方に暮れ、ため息をつくばかりです」と。
マオはこうした思いを四文字四行の漢詩(全五連)にまとめます。
最後の四行は以下の通り。
欲進無才(進まんと欲すれば才無く)
将退有逼(将に退かんとして逼らるる有り)
進退両間(進むと退くの両間に)
何夥歎息(何ぞ夥しき歎息をや)
進もうと思っても自分に才覚はなく、退こうとしても私に期待する親や親族が迫る。進むのか退くのか、その間にいてどうしてこんなにもたくさんため息が出るのだろう――と言うのです。
この何とも弱々しい言葉はどうでしょう。天才空海、自信家にして強い空海とはとても思えないひ弱さを露呈しています。しかし、これもまた(ある時期の)マオの偽らざる心中であったと思います。
その場はここまでの会話で別れたのでしょう。その後言い足りないと思ったか、マオはその人に次のような「手紙」をしたためます。
「現実の忠孝は狭い世界です。親への孝行、君主への忠義以上にもっと大きい仁徳があると思います。私は国家に対しても、父母に対しても、常に隠れた善行を向けようと努力しています。この国と家とに向けられた功徳の総和こそ忠孝なのです。一時的な不孝は長い目で見れば孝行になるときもあります。なのに、あなたは忠孝をただうやうやしくお辞儀することとのみ理解しています。なんと狭い見識でしょうか」と一見強い言葉を並べます。
しかし、最後に「とは言え、この手紙はまだ自分の心を充分述べ尽くしていません。後日改めて説明したいと思います」と記し、またも弱々しい側面をのぞかせるのです。
最後の原文は「然此書未委心」とあって「委細言い尽くせず無念」の思いさえ感じ取れます。
これこそ『聾瞽指帰』の中に私小説的要素(自身の情けない体験や告白)がまぎれ込んだ部分ではないでしょうか。
自信家と見える空海マオも、ある時期は儒教理論に対して堂々と反論できなかった。むしろ議論を交わしても言い負けたり、尻すぼみに終わる時期があったことをうかがわせます。
この部分から若き空海マオの弱さ、悩みが読み取れる。ならば、大学寮をやめるときだって迷いや悩みがあったと想像できます。
たとえば、現代の大学でも「もう大学にいたって仕方ない。ほんとはやめたい。けど、両親は自分に期待している。息子のために田舎で懸命に働いている。それを思うと、やめたいと言い出せない。でも、今の自分は大学にも行かず悪友とバカなことをやって遊び暮らしている」とめめしく悩む学生がいる。
そのようにマオも大学寮をやめたいと考えたとき、同じように悩んだのではないか。ある時期のマオはめめしくうじうじ悩む、弱々しい若者だったのではないかと思います。
これは私の勝手な空想ではなく、仏教編のこの部分から抽出した推理だったのです。
===================================
最後まで読んでいただきありがとうございました。
後記:103万円の壁が話題になっています。それ以上になると所得税がかかる。
まるでそれ以下の収入に対して無税であるかのような印象。本当に?
年間103万とはひと月8万数千円。このお金、共稼ぎ世帯やバイトの学生など普通生活費に使うでしょう。お米にパンにおかずの肉野菜。生活雑貨に嗜好品。すると常に10パーセントの消費税がかかる。つまり、103万までの収入全額に対して税金を払っているのと同じことです。
かくして103万以上で10パーセントの所得税が課されるということは(それを生活費に使う限り)合わせて20パーセントの税金を払っているのとイコールです。やれやれ。
===================================+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)
『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信
詳しくは → PDF版配信について
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
後半第 12 へ
→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録