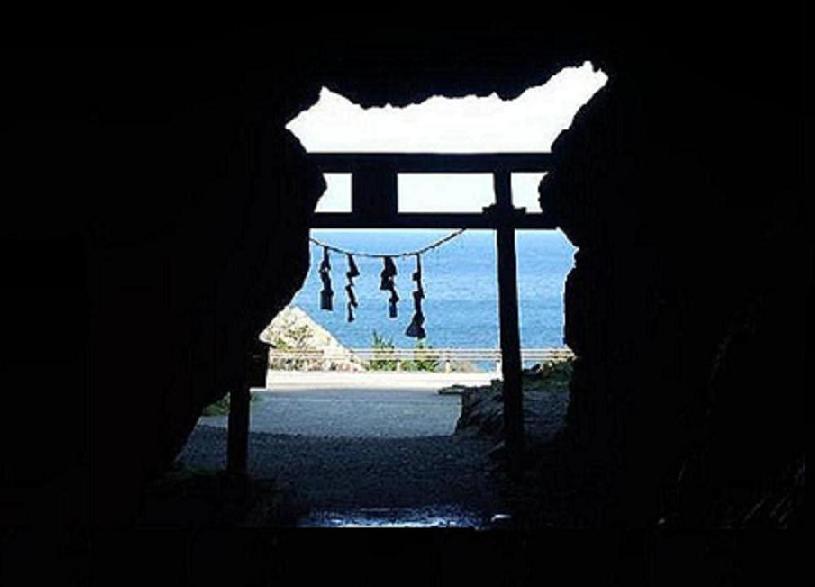
『空海マオの青春』論文編
後半第 9
プレ「後半」その4(二)-1
本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。
『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第279 ―論文編 後半09号
(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)
原則月1回 配信 2024年11月27日(水)
『空海マオの青春』論文編 後半 第9号 その4「『空海論』前半のまとめ(二)の1」
前半のまとめ二回目。空海の前期4つの謎について語ります。
今節は「空海を書こう」と思ったとき、何をどのように調べていったか。
過去の研究書・空海偉人伝、そして歴史書などを読み漁り、一読法で読みつつ、疑問や謎を書き留めた。その流れでもあります。
読者が十代の高校生や国文科の大学生なら、今節と次節はじっくり読んで参考にしてほしいところです。そして、読みの力がとてつもなく増大する(^_^)「一読法」をぜひマスターしてください。
→『 一読法を学べ――学校では国語の力がつかない 』目次
プレ「後半」その4 空海論 前半のまとめ
(一) 空海の前半生、前期(生誕〜23歳) 11月20日
(二) 前期4つの謎について(その1) 11月27日
前期4つの謎について(その2) 12月04日
(三) 空海の前半生、後期(24歳〜32歳)12月11日
(四) 後期3つの謎について 12月18日
(五) 帰国後の空海 12月25日
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
本号の難読漢字
・聾瞽指帰(ろうこしいき)・三教指帰(さんごうしいき)・三教(単独のときは「さんきょう」、儒教・道教・仏教)・勤操(ごんぞう、大安寺の僧、空海の師)・経蔵(きょうぞう)・便宜(検索を)
以下1〜5は『三教指帰』の登場人物
1 兎角(とかく)公 2 蛭牙公子(しつがこうし) 3 亀毛(きもう)先生 4 虚亡隠士(きょむいんし・亀毛先生と韻を踏めば「きょもういんじ」) 5 仮名乞児(かめいこつじ) 3は儒教、4は道教、5は仏教を語る。
・乱杭歯(らんくいば)・阿刀(あと)の大足(おおたり、空海の母方の叔父)・業(ごう)の報(むく)い・狎(な)れて侮(あなど)る[意味不明なら検索を]・六国史(りっこくし、『日本書紀』から始まる六冊の国史)・『続日本紀(しょくにほんぎ)』
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
***************** 空海マオの青春論文編 後半 ******************
後半第9号 プレ「後半」その4(二)「前期4つの謎について その1」
空海論前半における4つの謎を再掲すると以下の通り。
1 空海マオが幼い頃から仏教に進むと思っていたなら、なぜ官僚養成の大学
寮に入ったのか。大学寮の生活はどのようなもので、なぜ退学したのか。
2 奈良仏教に入門して何を考え、何を感じたか。なぜ山岳修行に走ったのか。
3 「聾瞽指帰」は空海にとってどのような位置にあるのか。なぜ儒教・道教・
仏教の三教を比較する必要があったのか。
4 二度の百万遍修行によって何をつかんだのか。改訂「三教指帰」と「聾瞽
指帰」はどのような関係にあるのか。
これらはたとえば司馬遼太郎『空海の風景』や他の研究書・偉人伝を読んで、「この疑問には答えていない」と感じた謎であり疑問です。
なぜ答えていないかと言えば、以前も書いたように空海自身の打ち明け話がない(チョー少ない)、傍証となるはずの同時代著名人の言及も(ほとんど)ない。
ならば、推理するしかないけれど、推理の根拠を明かさないまま語ることもできない。
中でも違和感を覚えたのは帰国後空海が示した人となり(たとえば、鎮護国家仏教を謳い、権力中枢と親密であったこと)を「若い頃もそうだったであろう」と、そのまま適用したことです。これは司馬遼太郎が最もはなはだしい。
たとえば、司馬氏は若いころの空海を評して以下のように書きます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「空海はこの中間階級出身者にふさわしい山っ気と覇気を生涯持続した」とか、大学寮入学頃のマオを評して「清らかな貴公子という印象からおよそ遠く、それどころか全体に脂っ気がねばっこく、異常な精気を感じさせる若者」と描く。
さらに、山野を歩く乞食僧空海は「いやみなほどに野心のみなぎった青年」であり、私度僧を続けることを「かれは境涯上苦節の人ではなく、まわりから必要以上なほどによく保護されていたのではないかと思える」と見る。(「 」内は『空海の風景』より)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
空海マオが四国讃岐の郡司の息子であり、中間階級出身であったことに間違いはありません。
だが、「山っ気と覇気を生涯持続した」となると、根拠を問いたくなります。
もちろん司馬氏に根拠はある。それは後年の空海が「そうだから」と言いたいのでしょう。
また、空海は大安寺に入門した後なかなか得度せず、私度僧のままでした(これも謎の一つ)。
司馬氏は空海が師匠勤操(ごんぞう)の「私的給仕人ではなかったか」と推理します。そして、空海はその立場によって「諸官寺の経蔵をひらいてもらう」便宜を得た。つまり、仏典を自由にたくさん読むことができた。
司馬氏はそれを評して「後年の空海の、ときに目をみはりたくなるほどのずるさが、このあたりにすでに出ている」と書きます。
後年の空海がずるかったかどうか――は置くとして「若い頃もそうだっただろう」と推理するわけです。
もちろん司馬氏も二十代前半の空海の苦悩を描出しています。破戒僧であったかもしれないと。
それでも司馬氏は「空海は強い人間」というイメージを終始持ち続けている。同氏は空海マオを《天才空海、強い人間空海》としてとらえている。『空海の風景』の中にめめしい涙を流す空海はいません。
私はそこに疑問を抱きました。はて、いくら天才的人間だからと言って悩みも迷いも持たない人間などいるだろうか、かつていただろうかと。
空海を書きたいと思ったとき、最初にかなり深く読み込んだのが『空海の風景』でした。全体的には名著だと思います。が、空海に対する――殊に若い頃の基本的認識、解釈に関しては上記のように大いに疑問がある。むしろ誤解していると思います。
同書はもちろん一読法で読みました。文庫本の余白に[!・?・◎・△]などをつけ、文中に傍線を引き、二度目は印をつけたところに注意しながら、自分の違和感を書き込み、長くなりそうなときはノートに抜き書きして自分の感想・意見を認める。
そして、同時並行的に読んだのが空海23歳の書『三教指帰』。空海の若い頃を知る書としてこれ以上ない一次資料だから。もちろんこれも一読法読書(^_^)。
このときすでに「あれっ」と思うおかしな表現を感じていました。
それは儒教・道教・仏教を「これこそ最高」と勧める三人の人物が内容は素晴らしいことを語っているのに、登場する様子がどうにもへんてこりんなのです。
同書は「三教を比較して仏教の優位を主張する思想書」と言われながら、戯曲的構成を持っています。
まずは「兎角公」が自堕落に生きる甥の「蛭牙公子」を矯正すべく、儒者「亀毛先生」宅を訪ねるところから劇は始まります。そこには道教道士の「虚亡隠士」も同席していた。兎角公は亀毛先生に「甥を改心させるにふさわしい教えをお聞きしたい」と申し入れる。
亀毛先生は「私にそのような資格はありません」と謙遜しつつ、「仁義忠孝は人の道であり、立身出世こそ現世の幸福をもたらす」と儒教を解説する。兎角公と蛭牙公子は聞いて感動を吐露し、以後は儒教を信奉したいと言う。
すると、そばで聞いていた虚亡隠士が「儒教などくだらぬ教えだ」と、儒教の問題点を指摘、無為自然、仙人を目指す道教こそ儒教を凌駕する。「仙人になればなんでもできるのだ」と神仙思想を力説する。兎角公と蛭牙公子、亀毛先生も感嘆する。
最後に乞食僧「仮名乞児」が登場して「儒教・道教は現世に限った浅薄な教えです。仏教は三世に渡る教えであり、二教の上をいく最高最上の教えです」と熱く語る。
兎角公と蛭牙公子はひれ伏し、最後は「仏教を信奉したい」として終わる。
面白いのは亀毛先生も虚亡隠士も「これからは仏教に宗旨替えしたい」というところです。
三者の語る内容は各自素晴らしいけれど、その人となりは奇妙です。
たとえば、儒者「亀毛先生」は言葉は立派なのに下に居丈高、上に卑屈な「おいおい」と言いたくなる人間として。かたや道教道士「虚亡隠士」は人を人とも思わない傲岸不遜な喋り方をする人間として描かれる。
最後に登場して仏教を語る「仮名乞児」は身なり貧しくやせ細った乱杭歯の乞食坊主。これを一言で言えば三者三様の「戯画化」が施されているのです。
私は戯画化に気づいたとき「なぜ?」と思いました。
また、兎角公が性根を叩き直したい若者として登場する蛭牙公子(母方の甥)は次のように描かれます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ここに一人の若者がいる。「その心は狼のようにねじけ、人から教えられても従わない。心が凶暴で、礼儀など何とも思わない。賭博を仕事にし、狩猟に熱中し、やくざでごろつきのならずもので、思いあがっている。仏教でいう因果の道理を信ぜず、業の報いを認めない。深酒を飲み、たらふく食べ、女色に耽り、いつまでも寝室にこもっている。親戚に病人があっても、心配などしないし、よその人に対応して敬う気持ちもない。父兄に狎れて侮り、徳のある老人を小馬鹿にする」ような人間である。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これまでの空海研究では「蛭牙公子のモデルは不明」とされていました。
儒者の亀毛先生は空海マオの母方の叔父「阿刀の大足」がモデル。仏教僧はもちろん空海自身。だが、他の人物はモデル不詳と。
私がここで「?」を記したのは「蛭牙公子はなぜ兎角公の息子ではなく甥なのか」でした。それもわざわざ「母方の甥」とされていました。
そして、『三教指帰』を丹念に読んだとき、ある部分に傍線を引きました。
同書は論文であり「儒道仏の三教を比較して仏教の優位を主張した思想書」として評価されています。
ところが、仏教編の中に奇妙な箇所があります。仏教僧仮名乞児の前に親戚が現れて「乞食坊主などやっていないで忠孝の儒教に帰れ」と叱責するのです。二人は儒教と仏教について論争します。
これはさーっと読む(^.^)と、仏教編の中に儒教論が紛れ込んだかに見えます。「下手な論文書いたなあ」とつぶやきたくなるところです。「これは一体どうしたことだろう」と疑問を抱きました。
そして、もう一つ同時並行的に読んだのが「六国史」の『続日本紀』と『日本後紀』です。
日本の歴史を朝廷が編纂する「史書」は『日本書紀』を最初として次に『続日本紀』、『日本後紀』と続きます。空海が生きた時代と重なるのが『続日本紀』であり、797年(平安遷都の3年後、空海23歳)に完成しています。その後のことは『日本後紀』(840年完成)でわかります。空海は835年62歳で入滅しているので、この2冊によって時代背景をかなり知ることができます。
以前も書いたように『空海伝』を描こうと思うなら、「時代背景」を知ることは必須。
当初は高校の日本史教科書、次に文庫本の「日本の歴史」奈良・平安時代編を読みました。「これで済ませるだろう」と高くくったけれど、ちっともイメージが湧かない。いわば「血湧き肉躍る」人物群が想像できない。
これらは当時の一次資料を読んだ研究者による書き物です。歴史的事実など全体像を知るには適しているけれど、当時の詳細を知ることは難しい。いわば、土中に埋もれた恐竜の化石のように、骨組みはわかるけれど、血が流れ肉や皮を持つ生の姿ではない。「一次資料を読むしかない」と決意しました。それが2冊の史書です。
私はトイレが長いので(^.^)トイレに常備して毎朝毎夕文庫を読んだ。もちろん鉛筆を握って「?・!・◎や〇△」をつけつつ読む。文中に傍線も引く。
一年経って初読が終わり、再読時は印をつけたところを念入りに読み直す。これは半年ほどで終わり、もう一度読みました。
二年後お尻から出血して(^_^;)「これはもう読まなくていい。書き始めろってことだろう」とつぶやいてトイレ読書をやめました。
史書二冊は大いに役立ちました。当時の(主として貴族ながら)人々の思いや感情を知ることができたからです。天皇家・朝廷の権力闘争、内乱、自然災害、東北蝦夷との戦い。その中を生きる天皇や貴族高官、庶民の感情。何より仏教・仏教界のこともたくさん書かれていました。
最も意外だったのは(空海は『三教指帰』によって「仏教こそ最高最上の教え」)と結論付けて仏教を勧めているけれど、朝廷も同じことを語っていたところです。
朝廷は「仏教こそ素晴らしい」として人々に「仏教を信奉せよ」と布告していました。「寝ているときも起きても般若心経をとなえよ」との一文さえありました。
私は「えっ、空海さんが仏教は素晴らしいと言ったって天皇・朝廷はすでにわかっているじゃないか」とつぶやいたものです。
これらの謎と疑問に関して解明したのが『空海論前半』全57節です。
そのまとめは次号以降といたします。
===================================
最後まで読んでいただきありがとうございました。
後記:米大リーグ大谷翔平が三度目のリーグМVPに輝きました。2年連続であり、指名打者として初の受賞。
解説を聞くと、「守り」のない指名打者は他の野手がプラス7〜8に対してマイナス16から始まるそうです。それをひっくり返すほどの活躍があったということで、素晴らしい。
おめでとうございます。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)
『空海マオの青春』小説編PDFファイル 無料 にて配信
詳しくは → PDF版配信について
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
後半第 10 へ
→『空海マオの青春』論文編メルマガ 読者登録