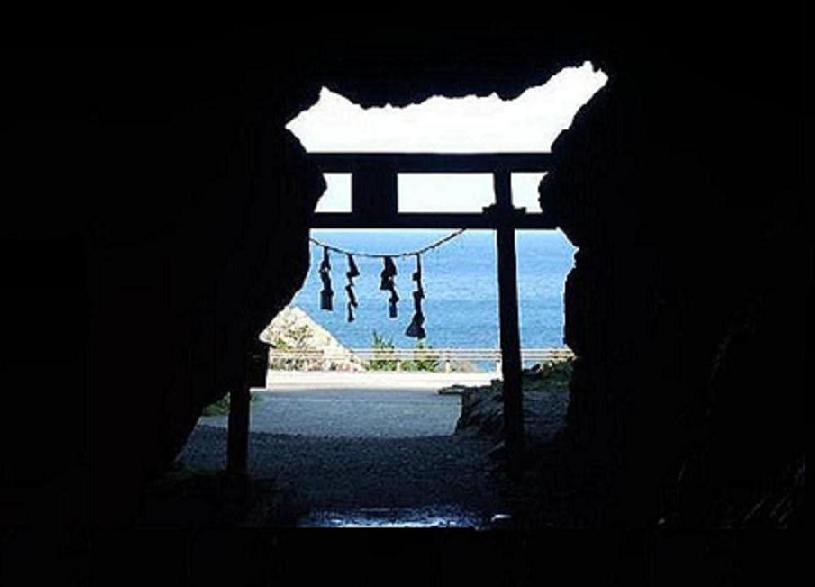
『空海マオの青春』論文編 第 37
「仏教回帰」その7
本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。
『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第114 ―論文編 37号
(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)
原則月1回 配信 2017年 3月10日(金)
『空海マオの青春』論文編
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−本号の難読漢字
・四弘誓願(しぐせいがん)・衆生(しゅじょう)・済度(さいど)・涅槃(ねはん)・声聞(しょうもん)・縁覚(えんがく)・上座部(じょうざぶ)仏教・『聾瞽指帰(ろうこしいき)』・鄭重(ていちょう)・承(うけたまわ)る・行脚(あんぎゃ)・披瀝(ひれき)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*********************** 空海マオの青春論文編 *********************************
『空海マオの青春』論文編――第37「仏教回帰」その7
第37「仏教回帰」その7 仏教入信の誓い、「四弘誓願」
まずは久し振りに雑談的伏線というか、伏線的余談から入ります(^_^)。
みなさんは自分が良いと思ったものを人に勧めるでしょうか。それとも、自分の中だけに閉じこめて勧めたりしないでしょうか。
たとえば、たまたまとあるレストランや居酒屋で食べた物がとてもおいしかった。あるいは、映画や本などとても面白かった、感動した。それを友人知人に知らせるかどうか。
昨今はブログ・ツイッター・インスタグラム全盛の世の中だから、「教える・知らせる」人が多いかもしれません。
しかし、これにはある危険というか、失望を味わう可能性が含まれています。
つまり、おいしいと思ったので知人に勧めた。知人は行って食べてみた。
ところが、「そんなにおいしくなかったよ」と言われる。
あるいは、あの映画、この小説にとても感激した。そこで「面白かった、良かったよ」と誰かに話した。すると後日「見たけど(読んだけど)、そんなに感じなかった」と返ってくる(-.-)。
人によって感じ方は違うからなあと思いつつ、若干の失望を禁じ得ない……なんてことがあるのではないでしょうか。
私は教員時代、自分が読んで感動した小説を生徒によく紹介しました。
しかし、あるとき「実は自分のベストワンは教えないんだ」と打ち明けたことがあります(^_^;)。理由は上に書いたようなことです。失望したくないからだと説明しました。
すると、放課後女子生徒が一人「紹介しないのはおかしいと思います」と職員室まで抗議に来ました(^_^;)。「それを読んだ人がどう感じようと、先生がいいと思ったのだから、それで良いではありませんか。先生が最も感動した作品も紹介してください」と言うのです(おお、言うじゃないか)。
振り返れば、私の話をとてもよく聴いてくれる生徒だったと思います。
でも、と私は応じました。「たとえば君が最も大切にしている物、それが多くの人から見たら価値のないがらくただったらどうだろう。これが私の宝物ですと言って見せたら、なんだがらくたかと思われたり、そんな物が宝なのかと言われたりする。君はたぶんがっかりするんじゃないか。だから、君の宝物は君の中だけに留めておいた方がいいんだ。私のベストワンもそれと同じだよ」と。
その子がどう答えたか、忘れました。ただ、私はその後も考えを変えず、二十数年間の教員生活において、自分が読んで最も感動したベスト1を生徒に紹介しないままでした(^_^;)。
さて、これを枕として本題の「四弘誓願」。
四弘誓願(しぐせいがん)とは菩薩に課された四つの誓いのことですが、信者となった仏教徒にも課されています。「弘」は「弘布(ぐぶ)」の「弘」。弘布とは広く大きく布教するとの意味です。まずはウィキペディアの解説をそのまま掲載します。
[ 四弘誓願 ]
1.衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)
……地上にいるあらゆる生き物をすべて救済するという誓願
2.煩悩無量誓願断(ぼんのうむりょうせいがんだん)
……煩悩は無量だが、すべて断つという誓願
3.法門無尽誓願智(ほうもんむじんせいがんち)
……法門は無尽だが、すべて知るという誓願
4.仏道無上誓願成(ぶつどうむじょうせいがんじょう)
……仏の道は無上だが、かならず成仏するという誓願
この四誓願、234は個人の誓いというか、仏教信仰における誓い・決意を述べているように受け取れます。煩悩を断ち、仏法を学び、必ず成仏するという誓いを立てようと。
ただ、1は若干違います。それは地上にいるあらゆる生き物――特に衆生(人間)を救済しようという誓いです。
1を中心としてもっとわかりやすく並べた四条もウィキペディアにありました。それが以下。
[ 四弘誓願 ]
1.未度の者を度せしめん……いまだ済度せざる者を済度せしめんとす。
2.未解の者を解せしめん……いまだ理解せざる者を理解せしめんとす。
3.未安の者を安ぜしめん……いまだ安心せざる者を安心せしめんとす。
4.未涅槃の者を涅槃せしめん……いまだ涅槃せざる者を涅槃せしめんとす。
この四誓願には全て「せしめん」という言葉が使われています。漢文で有名な使役形というやつで「〜させよう」の意味です。たとえば1なら、「いまだ救われていない人を救ってあげよう」といった意味合いです。
前の四項目では1に近く、いまだ救われていない者、いまだ仏法を理解していない者、いまだ安心の境地――涅槃・悟りの境地に達していない人を「救済せしめん」というのです。
何を理解させるのか、何を使って救済するのか。もちろん仏教であり、仏説でしょう。つまり、四弘誓願とは仏教を人々に広め、理解してもらい、いまだ安心の境地に達していない人に、安心の境地に達してもらおうとの誓いなのです。
簡単にまとめると、「仏教はとても良いものだから、入信しませんか」と人に勧める誓いであり、決意であると言えます。
ここで最初の余談雑談とつながったことがおわかりと思います(^_^)。
我々は《良いと思ったものを人に勧めるかどうか》です。
空海マオ――仏教は「仏説はとても良いものだから人に勧めなさい」と説いているのです。人々に弘布(ぐぶ)することを仏教入信者の願いとし、誓いにしなさいと言うのです。
空海は『三教指帰』仏教編において、四弘誓願の「四つの弘(おお)きな誓願はまだ完全に実現されて」いないと言います。
では、なぜ四弘誓願が必要か。もちろん苦しんでいる大衆のためです。「仏が『一子』と見なす一切衆生は、迷いの世界の溝に沈んでいる。このことを思うと悲痛な気持ちになり、かえすがえすも気がかりである」からだと。
要するに、仏教を知らない一般大衆は現世で苦しみ、死して地獄で苦しむ。仏法(仏教)を知って信心すれば、死後極楽へ行くことができる。この素晴らしい教えを大衆に知らせようではないか、と言うわけです。
我が宗教を大衆に勧める――これは仏教に限りません。全ての宗教・全ての主義に共通した願いであり誓いであるでしょう。自分がいいと思ったものを人に勧めたくなるのは、集団生活を営む人間の資質なのかもしれません。
話を宗教に限ると、四弘誓願はキリスト教やイスラム教、あるいは多くの新興宗教など、宗教全てが抱える課題です。すなわち「自分一人が入信すればそれで良いか、私が信仰する宗教を人に勧めるか」というテーマです。自分が良いと思ったものを人に勧めるか、それとも自分の中に留めることで良しとするか(^_^)。
ここには組織・集団と個人の関係もあります。多くの宗教(主義)信奉者は「自分が良いと思ったから人に勧める」のでしょう。一方、組織・集団の側は「我が宗教(主義)は良いものだから、お前は人に勧めるべきだ」と入信者に要求することになります。
これに関して仏教は二派に分かれました。
以前六道・十界について触れた時、六道を離脱した上部にあるのが仏界・菩薩界、声聞・縁覚の四界であると説明しました。
四界の中で上位二界の諸仏・菩薩は仏教を衆生に勧めている。対して下位の二界である声聞・縁覚は「自ら修行し、悟ればそれで良し」として、あくまで自分一人の悟りや解脱を求め、衆生に仏教を勧めることはないようです。
上座部仏教はそれで良しとします。だが、大乗仏教は「自分一人悟るだけでなく、苦しむ衆生に仏教を勧めるべきだ」と主張しているのです。
このテーマはキリスト教でも取り上げられ、『聖書』の中に金持ちの主人が家来三人にお金を預ける話として出てきます。
――主人は三人を呼び出し、一人に五タラント、もう一人に二タラント、そして三人目に一タラント預けて旅に出ます。一タラントは今なら三千万から五千万円くらいの価値があるそうです。
すると、一人目は五タラントを元手に商売をして2倍の十タラントにした。二タラントの者も2倍の四タラントに増やした。しかし、一タラント預かった者はそれを地面に埋めました。
やがて主人が帰ってきて三人にあの金はどうなったと聞きます。一人目、二人目は「預かった金を2倍にしました」と報告して「よくやった」と主人の祝福を受けます。
そして、三人目の家来が「私は一タラントを地面に埋めておきました。どうぞこれです」と言って一タラント差し出すと、主人は怒りました。「だったら、せめて銀行に預けてくれれば利息をもらえただろうに」と言って(^.^)。
私はこの話を二十歳の頃読んだ福永武彦『草の花』で知りました。主人公「汐見」は愛する千枝子と宗教をめぐって議論します。千枝子はキリスト教を深く信仰しています。
汐見は「私は一タラントを地面に埋めた家来は間違っていないと思う。確かに増やせなかった。だが、減らすこともなかった。信仰したら必ず信者を増やさねばならないのだろうか。自分一人の中に閉じこめてもいいではないか」と言います(内容はまとめています)。
ところが、千枝子は自分が良いと信じるものを他に分かち与えれば、それによって喜びを共有でき、さらに深い信仰として育まれる。これは神の愛にかなうのだと反論しました。
千枝子はキリスト教を人に勧めるべきだと思う。汐見もキリスト教が良いとわかっている。けれども、自分の中に留めるだけでいいではないかと言うのです。
作品全体で見ると、ここには《孤独》をどうとらえるか――その問題も絡んでいます。
ひとりぼっちがさみしいから誰か(特に異性)と一緒になって孤独を分かち合いたいと思う。しかし、二人で暮らし始めると、今度は孤独が無性に懐かしくなる、といった感覚でしょうか。
二人がその後どうなったかは本をお読みください。ちなみに『草の花』は私のベスト5の一冊ですが、ベスト1ではありません(^_^)。
レストランの食事や映画、本などはさほど考えることなく人に勧めるとしても、宗教とか主義を人に勧めるかどうかはかなり悩ましい問題です。
私がこのテーマを初めて意識したのは二十歳前後のことでした。大学時代、私は精神的なことで悩み自殺まで考えました。その頃周囲を見渡せば、宗教と主義に飛び込んで、生き甲斐や充実感をもって活動している学友が何人もいました。
宗教ではキリスト教系、新興仏教系、主義ではやはり社会主義系、共産主義系。彼らと言葉を交わせば、最終的な結論はだいたい同じでした。「我が宗教、我が主義は素晴らしい。これに入ってともに活動しよう。そうすれば君の悩みは解消できる」と言うのです。
その頃私の疑問はこうでした。「彼らはなぜそれを信じることができるのだろう。どうして自分は信じることができないのだろう」と。
私には宗教も主義も同じに見え、彼らはそれを良いと信じて活動している、生き生きと充実感を持って活動している。それゆえ彼らが信じる宗教、主義を人に勧めている、そう思いました。
ところが、私はいずれも信じることができませんでした。そして、信じることができそうもない自分に絶望し、結局宗教にも主義にも飛び込むことができませんでした。かと言って臆病だから自殺もできませんでした。
結局、私は『草の花』の汐見のように、良いものは自分の中だけにとどめることにしました。かくして愛読書ベストワンを生徒に教えなかった――とつながります(^_^;)。
しかし、この回顧話、ちょっとかっこつけすぎです。汐見は信仰を心に閉じこめました。私の場合は閉じこめるべき何ものも持っていませんでした。信仰はなく主義もなく、信条はなく、処世訓も持っていませんでした。
そういう人間がどうして高校教員を続けることができたのか。その辺の話はいろいろありますが、後日として本題の「四弘誓願」に戻ります。
空海マオは儒教、道教を経て仏教にたどり着いた。これこそ最上のものとして衆生に仏教を進めるべく四弘誓願の誓いを立てました。その一つの現れが『聾瞽指帰』執筆でしょう。
空海は仏教編の最後で仮名乞児に語らせています。
まず儒教・道教について「かの道教の仙人の小さな方術、儒教の俗にまみれた微々たる教えなどまったく言うに足りないものであり、立派とするにはあたいしないものである」と批判して「仏教によって理想社会を実現できる」と言います。
「かの仏陀が同一の言葉で妙なる説法をおこなって人々の愚かな我執を打ちくだき〜甘露(めぐみ)の雨をふらせて衆生をみちびき戒め、仏法を聞く喜びを心の糧として、そのなかに智慧と戒律をくるめ、一切衆生が太平の世を謳歌して〜帝王の功績を意識しない理想の社会を実現」できると。
かくして仮名乞児の仏説を聞いた亀毛先生らは「喜び、踊りあがって」次のように言います。
「わたくしたちは幸運にも遇(あ)いがたい大導師にお目にかかることができ、鄭重に出世間の最もすぐれた教えすなわち仏法について承ることができました。これは昔にも聞いたことがなく、後世にもまた聞くことのできないものです。〜かの周公・孔子の儒教や老子・荘子の道教などは、なんと一面的で浅薄なものであることか。今からのちは〜大和尚の慈愛あふれるみ教えを書きしるして、生まれかわり立ちかえる後々の世まで悟りの世界に向かう船とも車とも致したいと思います」と。
儒教、道教を経て仏教にたどり着いた若き空海はここで一つの結論に達しています。仮名乞児が説く仏教は現代の仏教事典を見たかのように漏れがありません。
ぶっちゃけ、今なら私でも書けるかも知れません(^_^;)。しかし、仏教入門書や百科事典、ネット事典などなかった時代です。他の漢籍を取り入れ、巧みな比喩を交えて完璧な仏教入門書を書き上げるなんぞ、驚異的な才能と言うしかありません。空海マオは仏教のイロハを書き尽くし、まとめ尽くしたと思います。
そうなると、今後はこの仏教を人に勧めるべく行動を始める――当然《四弘誓願》の誓いを実践すべきでしょう。大衆は空海の仏説を聞けば、「素晴らしい教えです。私も入信いたします」と応じてくれるはずです。ところが……
空海は『聾瞽指帰』を公表しません。また、果たして仏教を説くべく全国行脚の旅に出たかと言えば、おそらくそれもなかっただろうと思います。
忘れていけないのは空海が仏教界に飛び込んだ理由です。叔父大足の勧めに従って「腐った仏教界に対して新しい仏教をつくりたい」との思いでした。『聾瞽指帰』は三教比較の仏教入門書ではあっても、新しい仏教は何も描かれていません。
ここんところ、蛭牙公子・兎角公・亀毛先生・虚亡隠士らが《頭を丸めた仏教僧を初めて見、仏説を生まれて初めて聞く》と構想されたことはとても象徴的です。
仏説を初めて聞いた人なら、我が仏説に感激してくれるかもしれない。これを逆に言うと、仏教をよく知っている人は彼らのように感動してくれない、儒教・道教信奉者は簡単に宗旨替えしてくれない――空海は「もちろんそれはわかっていますよ」と白状しているように思えます。
ここらへんの事情は次号「仏教弘布(ぐぶ)の悩み」に回します。
===================================
最後まで読んでいただきありがとうございました。
後記:聖書の挿話をもう少し補足しておきます。これは組織と個人の関係で言うと、組織の側が預かった金を2倍にした――つまり信奉者を増やした者を賞賛するお話でもあります。神は我が宗教を広めた者を祝福してくれる。それは信者の努めでもあると言いたいようです。
主人は家来三人に5、2、1タラントと渡しています。ということは三人の能力に差があることをわかっていた。別に無理な要求はしていない。それぞれの力に応じて「それを増やしてくれ」と言っているだけ。そして、二人はその期待に応えた。だが、地面に埋めるなんて「とんでもない」と言いたいようです。
では、なぜ三人目の家来は預かった金を地面に埋めたのでしょう。その理由を述べた部分が以下。
彼は「ご主人さま。あなたは蒔かない所から刈り取り、散らさない所から集めるようなひどい方です。私はこわくなってあなたの1タラントを地面に隠しました」と言います。
この家来の言葉、難解です(^_^;)。私はキリスト教の専門家ではないので、興味のある方はネット解説などで探求なさってください。
ただ、私なりに考えたところを披瀝してみると……
そもそも種をまかなければ、実りはなく何も収穫できません。1タラントとはその種でしょう。主人は種を渡すことなく増やせと無理なことを言ったわけではありません。なのに、蒔かない所から刈り取るような人だなんて、家来の言葉は言いがかりというか、妙な言い訳です。
しかし、もしもその金を増やすことができなかったら、と考えてみます。主人は「せめて銀行に預けてくれれば利息をもらえただろうに」と嘆いています。ということは何か商売をやって1タラントを減らしたら、主人は「いいよ、いいよ。あることだよ」と言ってくれる人でしょうか。
そもそも銀行だって安泰とは限りません。金を預けた銀行が倒産したら、利息どころか1タラントは消えてしまいます。そのときこの主人は「どうして銀行に預けたんだ」と怒るかもしれません。
つまり、この主人は増やすことしか考えておらず、減らすことは決して許さないような人間だ――三人目の家来はそう思ったのでしょう。だから、増やすことはないけれど、減らすこともしない道を選んだ……のではないかと思います。1タラントを地面に隠すとは、このように解釈できるかもしれません。
神は、仏は、宗教は、主義は、文明は、科学は――そこに関わり熱中する人間は、増やすこと、進歩すること・拡大することしか考えていない。この話をそう理解すると、なんとも深いお話だと感じます(^_^)。
===================================+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)
『空海マオの青春』小説編配信終了 論文編連載中
小説編PDFファイル
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++