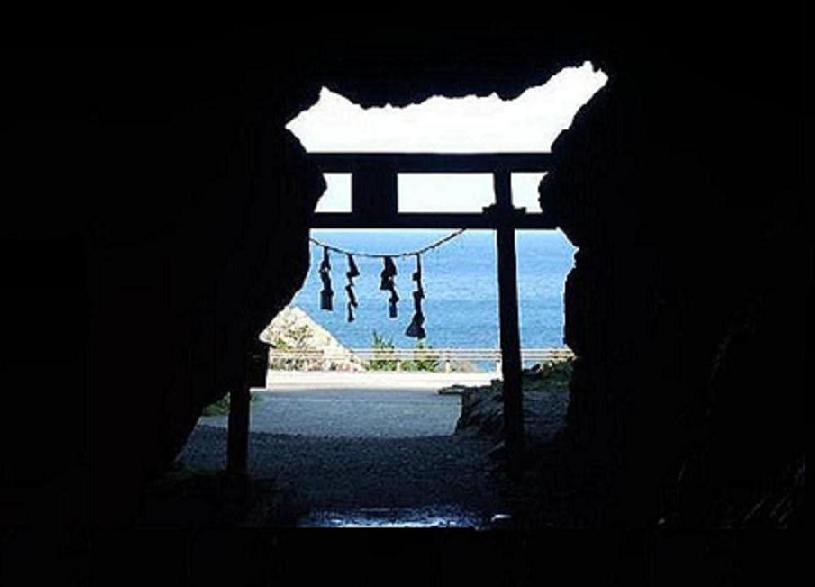
『空海マオの青春』論文編 第 34
「仏教回帰」その4
本作は『空海マオの青春』小説編に続く論文編です。空海の少年期・青年期の謎をいかに解いたか。空海をなぜあのような姿に描いたのか――その探求結果を明かしていきます。空海は何をつかみ、人々に何を説いたのか。私の理解した範囲で仏教・密教についても解説したいと思います。
『 空海マオの青春 』論文編 御影祐の電子書籍 第111 ―論文編 34号
(^o^)(-_-;)(^_-)(-_-;)(^_-)(~o~)(*_*)(^_^)(+_+)(>_<)(^o^)(ΘΘ)(^_^;)(^.^)(-_-)(^o^)(-_-;)(^_-)(^_-)
原則月1回 配信 2016年12月10日(土)
『空海マオの青春』論文編
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−本号の難読漢字
・現世利益(げんぜりやく)・声聞(しょうもん)・縁覚(えんがく)上座部(じょうざぶ)仏教・兜卒天(とそつてん)・衆生済度(しゅじょうさいど)・出世間(しゅっせけん)・五衰(ごすい)・従容(しょうよう)・達磨禅師(だるまぜんじ)・嵩山(すうざん、中国の高山)・役行者小角(えんのぎょうじゃおづぬ)・太澄聖人(たいちょうしょうにん)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*********************** 空海マオの青春論文編 *********************************
『空海マオの青春』論文編――第34「仏教回帰」その4
第34「仏教回帰」その4 六道+四界=「十界」について
これまで六道について詳しく眺めました。
仏教は説きます。人は迷いの世界である六道を輪廻転生するのではなく、六道を離脱して極楽を目指すべきだ。でなければ、人は四苦八苦の海に溺れ、救われることはないと。
六道の中には仏教を守って闘う阿修羅や、仏教を守護し現世利益を説く天人も入っています。しかし、彼らが住む世界は極楽ではない。以前書いたように、それはまるで「仏教に入信するだけではダメだ」・「仏教を守ることを名目として武器を持つことまかりならん」と言わんばかりです。
私は四苦八苦とは四喜八喜でもあると思っています。しかし、日々の人間関係において大なり小なり苦しみが生まれることは間違いありません。
逆に言うと、苦しみはほとんど人間関係によって起こるのだから、人間界を離れれば苦は起こらない。すなわち、無人島に一人で暮らせば(充分な食糧が得られるなら)、人間関係による苦しみは皆無となるはずです。
仏教は「無人島に行きなさい」とは言いません。しかし、山奥など人間界を離れて修行に励むなら、それがすなわち六道を離脱し、極楽に至る道の一歩であると見なしています。
人里離れたところで修行する人たちを声聞・縁覚と呼んでいます。さらにその上部に目指す菩薩界、仏界がある。仏教では六道とこの四界を合わせて《十界》と呼びます。以下六道の復讐も兼ねて十界全体を掲載します。
《十 界》[六道を脱して極楽・浄土へ]
1 仏 界……苦しみのない極楽・浄土・涅槃であり、三千世界の仏陀が住む
2 菩薩界……すでに仏だが、衆生済度のため菩薩にとどまっている
3 声聞界……仏教を学び修行する(ことで満足している)人たち
4 縁覚界……師はいないが修行を積む(自ら悟ったと称する)人たち
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
《六道》[迷いの世界]
1 天人界……仏教を弘布・守護する天人が住む
2 人間界……貪瞋癡に苦しむ人間が住む
3 修羅界……仏教を守護し闘い続け、負け続ける阿修羅が住む
4 畜生界……人に使役される牛馬が住む
5 餓鬼界……常に飲み物食べ物を求めて得られぬ餓鬼が住む
6 地獄界……各種地獄で責め苦を受ける罪人が住む
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ちょっと不可解なのは、前号で触れたように菩薩は天人界に住んでいることです。たとえば、仏陀の後継者とされる弥勒菩薩は天人界中の欲界、さらにその中の兜率天に住んでいる。
しかし、同じ天人界に住む七福神や四天王などは仏ではなく、弥勒菩薩は「もう仏である」と見なされています。この違いは一体どこにあるのでしょう。目下研究中です。
それはさておき、十界を大きく分けるなら、六道は迷いの世界であり、苦しみがある。しかし、上部の四界に迷いはなく、苦しみはない――と言い切れるかどうか微妙ながら、取りあえず「苦しみはない」と言っておきます。
十界の最上部が目指す仏界であり、その下が菩薩界です。仏界には四如来(阿弥陀・大日・薬師・釈迦)をはじめとする三千世界の諸仏が住んでいます。仏とは解脱を成し遂げた存在であり、衆生を見守り仏教を説いています。
その下に観音菩薩や普賢菩薩、仏陀の後継者と言われる弥勒菩薩が住む菩薩界があります。これがどうも天界の中ではなかろうかと思われます。少なくとも弥勒菩薩は天界に住んでいます。
菩薩とはすでに六道を脱して仏になる資格を得られた方々。しかし、仏にならず衆生済度のため現世にとどまっている。すなわち寿命がある。ならばやはり天界に住んでいると思われます。菩薩と四天王・七福神は何がどう違うのか、気になります。
この問題はいつかまた取り上げることにして、今号では声聞・縁覚について掘り下げたいと思います。
仏界・菩薩界の下にあるとされる声聞界、縁覚界。縁覚は自ら修行を積んで悟った者、声聞は仏教を学び苦行を続ける者――とまとめることができます。通常「声聞・縁覚」というように並び称されることが多いようです。
上記説明文中「修行することで満足している」・「自ら悟ったと称する」を( )に入れたのは、大乗仏教の側の批判だからです。おそらく声聞・縁覚の方々はそう思っていないでしょう。
大ざっぱに言うなら、声聞・縁覚とは修行重視の「上座部仏教(小乗仏教)」の該当者であり、大乗仏教の側は「声聞・縁覚にとどまっていては極楽に行けない」と批判しているのです。
なのに、声聞・縁覚は六道を離れ、六道の上部に置かれています。
そのわけは最初に書いたように、人間関係を断捨離する(切り離す)からでしょう。たとえば、滝行・山岳修行に座禅修行、あるいはインドのヨガの苦行など、修行はだいたい人里離れたところで行われる。必然的に人間関係を離脱することになり、離脱すれば苦しみは減る。苦しみが減れば、菩薩・仏により近づくことができる――そういう意味で声聞・縁覚も六道を離れた高位に置かれているのだと思います。
日本では「出家」とか「出世間」と言います。取りあえず家を出て仏門に入る。それによって四苦八苦を逃れる。逆に言えば、人間関係にまみれて暮らす限り、解脱や救いを得ることは難しい。よって「仏門(宗教)に入るしかない」とも言えます。
明治の文豪夏目漱石は苦しみから逃れる方法は三つしかないと言いました。「死ぬか、気が狂うか、宗教に入るか」だと。
僭越ながら漱石大先生に反論申し上げると、私はもう一つあると思っています。それが空海の説いた《全肯定》です。喜びはもちろんのこと、あらゆる事態、あらゆる悲しみ・苦しみを肯定して受け入れる。理屈として受け入れるだけでなく、心から許して受け入れる。それによって心の平安を得ることができる。
このことを知ったので、私は空海を小説に書こうと思い、こうして論文まで認めています(^_^)。
ところで、十界全体をどう解釈するか、考えるといろいろ疑問が湧いてきます。
まずとても素朴な疑問としては「地獄は本当にあるのか、極楽は実在するのか」という、素朴と言うより根本的な疑問です。そして、現世利益を説く天人と仏界・菩薩界の方々はどう違うのか。弥勒菩薩は天人界の最下層である欲界の兜卒天に住むとありました。ということは天界とはやはり極楽なのか、天界とは別に菩薩界や極楽浄土があるのか等々。
かつて地獄も極楽も実在すると信じられた時代があります。現代では仏教の熱烈な信者でもない限り、地獄極楽があると信じている人は少ないでしょう。
また、諸仏と天人との違いは前者に寿命がなく、永遠の存在であるのに対し、天人には寿命があり、死の直前に地獄以上の苦しみがあるとされていることです(ここで新たに起こる疑問は「なぜ天人にそのような苦しみを想定しているのか」ですが、答えは探索中です)。
そもそも仏陀の後継者とされる弥勒菩薩にも寿命がある。よって、天人の一人である。ならば、弥勒菩薩が死ぬとき、五衰現象の苦しみが起こるはず。さらに、六道のいずれに生まれ変わるかが問題となります。しかし、弥勒菩薩だけは人間界に生まれ変わることが約束されている。彼は衆生に対して極楽浄土に生まれ変わるための「仏法」を説くのでしょう。
推測するに、すでに仏であるなら、弥勒菩薩は天人最後の五衰現象など苦痛とは感じず、人間として生まれ変わることもいやだなどと思いもしないのでしょう。
もしかしたら、そこが天人と菩薩を分けている違いかもしれません。一般天人は五衰現象を苦痛と感じ、生まれ変わる世界に不安や嫌悪、恐怖を覚える。だが、菩薩は従容としてその全てを受け入れ、心乱れることはない……というような(^_^)。
おやー、これはもしかしたら、菩薩と天人を分ける違いかもしれません。天人には全肯定がない。が、菩薩には全肯定がある。言い換えれば、全肯定の境地に達した天人が菩薩になるんだ、と。
いや、今思いだしたことがあります。人は生まれ変わったとき、前世の記憶が消されます。ならば、弥勒菩薩だって人として生まれ変わったとき、前世は弥勒菩薩であることを知らない――忘れているはずです。ということはごく普通の赤ん坊として生まれるのではないか。
うーん。これは小説のテーマになりそうです。人として生まれた弥勒菩薩は幼い頃から仏陀の証を見せるのか。あるいは、ゴータマ・シッダルタのように人生に悩み苦しみ、仏教修行に励んだ後、釈迦の後継者として名乗りを上げるのか。今から五億年後人類が存続しているなら、その世界が見られるかもしれません(^_^)。
また、雑談が過ぎてしまいました。
閑話休題。十界に関する解釈について「十界とは現実にある世界ではなく、人間そのもの、心の状態を表現している」との見方があります。六道については前号にて触れましたが、再度詳しく説明します。
人は生きて苦しんでいる。働いて牛馬のようにこき使われ、眠ることと食べることしか休息がなければ、それは畜生と同じ。あれがほしいこれがほしいと飢え渇え、次から次に欲しい物を買い求め、あげく借金の山をこしらえて苦しんでいるなら、それは餓鬼と同じ。愛して欲しい、愛が欲しいと求めて得られないなら、それも餓鬼道。
あるいは、さまざまな事故に遭い、鉄の塊に押しつぶされ、ナイフや包丁で刺され、火事で焼け死ねば、それこそ地獄。人と人が殺し合う戦争は地獄の最たる姿でしょう。
さらに、自分のために闘い、家族のために闘い、会社や組織、国のために闘って心休まるときがなければ、それこそ阿修羅。最後はぼろぞうきんのようになって「自分は一体なんのために闘ってきたのだろう」と振り返る。そして、阿修羅像のような悲しい目になる……。
要するに、六道とは人間そのもの、社会そのものを描いているとの解釈です。
天界の天人もやはり人間。それは世界の1パーセントにも満たない富裕層と呼ばれる人々。使い切れないほどの金を持ち、高級料理に舌鼓を打ち、プール付きの豪邸かタワーマンションの最上階に住み、欲しい物はなんでも手に入る。それは正に現世の極楽。我が世の春を謳歌しているでしょう。
だが、やがてやって来る「天人五衰」――富裕層の方々にも老いや死が近づく。この世が極楽なんだから死にたくないでしょう。不安や恐怖は一般大衆と比べると正に十数倍になる。
もしも富裕層が仏教(あるいは、キリスト教、あるいはイスラム教など)を信仰して一般大衆に「我が宗教」を勧めたとしたらどうでしょう。彼らは極楽に行けるだろうか……答えは明らかだと思います。
六道=人間の全体と取れば、すなわち生老病死であり、正しく四苦八苦の人生です。
そして、これ以上生きていけない。死ぬか気が狂うか――と思って自死の道を選べば世界は終わります。ほんとうに精神病となるか、薬中・アル中となって人間をやめるか。
もう一つ残された道が人間界を離れること。人里離れたところで修行に入れば縁覚であり、仏教を学んで修行すれば声聞となる。そうして菩薩・仏を目指す――このようにまとめることができます。
ここで新たな疑問が湧きます。
なるほど声聞・縁覚は仏界に至る道でしょう。しかし、世間を離れて修行に入ったとして苦しみはなくなるのでしょうか。
もちろんそれまであった人間関係による苦しみはなくなるでしょう。しかし、彼らは新たな苦しみを抱えるはずです。それは「悟れるかどうか」であり、「仏になれるかどうか」です。どうやって食べていくかという根底の課題もあります。
ダルマさんで有名な中国禅宗の開祖達磨(ダルマ)は「面壁九年」として有名です。中国南北朝時代の僧侶、達磨禅師が嵩山(すうざん)少林寺に籠もり、九年間壁に向かって座禅を組み、ついに悟りを得たという話です。
ここには二つの問題があります。九年間生きるためには何か食べなければなりません。達磨自身が生産活動を行っていなければ、誰か――普通に考えれば寺が食物を用意したはず。
では、寺はそこで暮らす僧侶や修行僧の食物をどうやって手に入れたか。これも自分たちで田や畑を耕して自給自足生活をしない限り、外部の大衆から寄進という形で食物を得たでしょう。その中には国が(仏教を保護・勧奨していれば)食物を寄進・支給したかもしれません。
ということは厳密に言うと、寺院は人間界、世間から離れていません。修行者は「そんなのカンケーねえ。オレは座禅を通じて悟りを目指すのだ」と言うのでしょうか。
もう一つの問題はその悟りです。達磨は面壁九年によって「悟りを得た」と言われます。
日本でも役行者小角や白山太澄聖人など、「厳しい修行によって悟りを得た」と言われる聖人がいます。
さて、修行者当人が「悟りを得た」ことはどうやって証明されるのでしょう。
悟り試験でもあるのでしょうか。もちろんそんなものはありません。
悟りとはつまるところ精神的な状態であり、客観的に認定できるものではありません。それゆえ、基本的に当人が「悟りを得た」と言えば、周囲はそれを認めるしかないようです。
このように考えを進めてくると、そもそも人は生きて悟ることは可能なのか。生きて菩薩界・仏界に行くことはできるのか、これが大問題となります。
いやいや、生きたまま菩薩、仏になることなぞ不可能であり、死んでようやくその世界に行けるのだ――となって「成仏」なる言葉が生まれました。仏に成るとはイコール死ぬことである。死ぬことでやっと仏になれるというのです。
そこで、十界全体を一人の人間と見なして作成し直すと次のようになります。
《十界を一人の人間から見直す》
仏・菩薩(極楽・浄土・涅槃)
↑死後
声聞・縁覚(世を離れて苦行・修行を続ける)
↑出世間
人間(生まれて死ぬまで
要するに、人として人間界・社会の中で生きてゆく限り、苦しみから逃れることはできない。出家して仏道修行に励めば、とりあえず苦しみから脱することができる。しかし、修行を続けたとしても菩薩や仏になることはなく、死後ようやく極楽へ行けるというわけです。
もちろん仏教は何もしないで「死ねば誰でも仏になれる」とは言いません。
その具体的な内容は次号といたします。
===================================
後記:今年も空海論文編を読んでいただき、ありがとうございました。
本年は大きな変動の節目となる年だったかもしれません。民族大移動とも言われる難民の欧州流入、イギリスのEU離脱、グローバリズムへの反感、ナショナリズム・民族主義の台頭と右傾化、独裁的なリーダーの誕生等々。そして、日本でも同じような流れであり、ヘイトスピーチ、いじめ自殺、差別偏見による大量殺人もありました。
昨年「ありのままに」があれだけ歌われたのに、ありのままを認めるどころか、否定・抹殺する人が増えているように感じます。実は《ありのまま》こそ《全肯定》なのですが、人々の感情にしみこむのはまだまだ先のようです。そうした時代を悲観視するのではなく、ありのままに認める――それも全肯定だと思います。
世界と皆様方に良いことが起こることを祈念して来年もよろしくお願いいたします。m(_ _)m
===================================
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MYCM:御影祐の最新小説(弘法大師空海の少年期・青年期を描いた)
『空海マオの青春』小説編配信終了 論文編連載中
小説編PDFファイル500円にて販売 詳しくは → PDF版販売について
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++